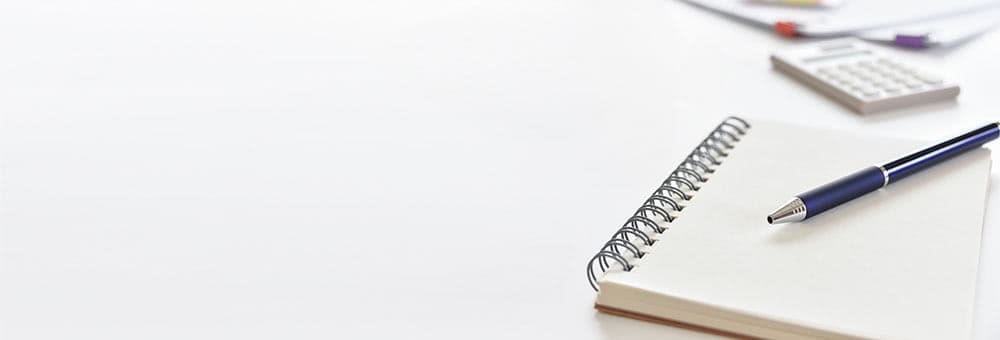仕置きが終わった以上、もはやそのことは決着がついている
●「黄門様」として、日本人に根強い人気を持つ徳川光圀は、人情の機微を心得た名君であった。光圀は家臣たちの誰かが罪を犯して処罰されても、許されたあとはまったく問題にせず、ほかの家臣たちと同様に扱った。
●光圀は、部下の育成、指導にあたって、その短所や過失は極力問題にせず、もっぱら長所をみて伸ばしていく方針をとっていたのである。
●だから家臣たちは、光圀のもとで、長所や能力を伸ばし、短所を克服するよう心がけることができた。
●そうした教育方針であったため、罪を許されたのちも、「あの者はかつて、このようなおとがめを受けたことがある」などと陰口をき
くのをひどくきらった。そこで、タイトルの言葉によって、諭したのである。
●一度や二度の失敗をいつまでもむしかえし、陰口をたたき、二度と浮かび上がれないようにしたり、組織のなかにいたたまれないようにすることは、人の上に立つもののなすべきことではない。また、部下たちがそうするのを許しておくべきではない。
●一度や二度の失敗、過失ぐらい、教育のチャンスに生かし、許すぐらいの度量がなくては、管理者として大成できないのではないだろうか。
●人使いの名人であった経団連名誉会長の土光敏夫は、異動や昇進の評価をする際に、えてして過去の失敗や不行跡を引き合いに出しやすい、として、次のようにいましめている。
●「このような発想には根本に人間不信感があるのだが、たとえ不信感を与えた事実があっても、人間は変わりうるという信念を欠いている点が重大だ。人によっては、失敗や不行跡を契機として転身することもあるし、旧弊をかなぐり捨てて翻然と悟ることだってある」
●そして、人間を変えるうえで、人の上に立つ者の影響が大きい点を指摘し、部下の育成、指導を誤らないようにと助言している。