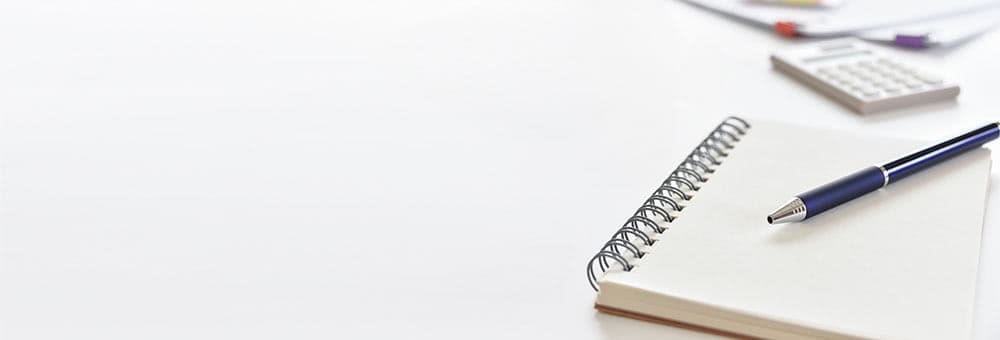往く者は追わず、来たる者は拒まず
●「自分のところを去るものは去るにまかせ、自分のところにやってくるものは、その人の過去や世評にこだわることなく快く迎える」
という意味。
●孟子が滕(しつ)という小国へ出向き、迎賓館に泊まった。館の人がわらじを窓際におきっぱなしにしていたら、それがなくなった。
●「先生のお伴の人がもって行ったのでしょう。ひどいことをしますな」
と、ある男が非難した。すると孟子はこういった。
●「あなたは、連中がわらじを盗むために私についてきたと思っているのですか。そんなことは考えられませんが、よしんばそうであ
っても構いませぬ。わたしは、弟子をとるとき、去るものは追わず、来たる者は拒まず、ということにしています。学ぶ意志さえあれば、誰でも弟子にしています」
●この言葉は、教育者としての心がけを述べたものである。
●ビジネス社会は、学校と違って競争原理の上に立つ。また、管理者や経営者は教育者と違うから、この言葉どおりにするのは難しい。しかし、リーダーたる者は、部下に対しては、教育者と同じ心がけをもつことが望ましいのである。
●企業が社員を採用するに当たって、
「来る者は拒まず」
という姿勢をとることは難しい。採用人員には制限があるし、入社希望者をすべて迎え入れるのは不可能に近い。
●だが、社員はこの企業を終身の職場と思って入社したものである。彼らはこの企業と生死をともにするつもりで近寄ってきたのだ
したがって、リーダーたるものは、部下に対しては、すべてを許容する心がけで指導教育すべきなのである。
●去るものを追わないということは、心がけさえすれば、なんとかできる。使う者としては、この部下は惜しいと思うかもしれないが、いくら能力のある者でも、すでに心が離れている以上、執着すれば、こちらがみじめになるだけである。